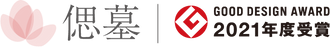地図
| 所在地 | 三重県多気郡多気町神坂169 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR「多気」駅 |
| 交通案内 | JR「多気」駅から車で10分 |

お寺の紹介
ご挨拶

ご相談から納骨までの流れ
ご相談から墓石の制作・納骨まで、約2ヶ月で供養が始まります。
STEP1
相談・資料請求

まずは資料請求をしてください。ご請求より数日でご自宅に資料をお届けいたします。
STEP2
寺院見学

実際に見学して立地や宗派、住職の人柄などをご確認ください。
STEP3
お申し込み

お申し込みは郵送で行う方法とWEBから行う方法をご用意しておりますので、お客さまのご都合の良い方からお申し込みください。
STEP4
納骨

お申し込みから1か月程度で墓石が完成します。遺骨を寺院にお持ちいただき納骨します。
最短1〜2ヶ月
よくある質問
Q:従来の「納骨堂」との違いは?
A:屋内に遺骨を安置する納骨堂に対して、偲墓(しぼ)は従来のお墓と同じように屋外に安置されるため、いつでも気軽にお墓参りができます。また、日々の供養や年忌法要が料金に含まれる点でも異なります。
Q:解約したらどうなりますか?
A:解約後は偲墓(しぼ)を設置していた寺院の永代供養墓にて永続的に供養いたします。または、ご遺族様に遺骨をお返しすることも可能です。
Q:基本料金以外に費用は必要ですか?
A:基本料金以外の諸費用及び追加費用はかかりません。永代供養料も含まれています。また、お布施やご寄付の強制もありません。
Q:後継者がいない場合はどうなりますか?
A:最終的にはお申し込みいただいている寺院の永代供養墓にて合祀させていただきます。その後は費用をいただくこと無く、永代に渡って供養させていただきます。
Q:申込後に引っ越すことになりました。どうすればよいですか?
A:偲墓では提携寺院間の墓石の移動に対応しています。引越し先に近い提携寺院をご紹介させていただきます。
Q:宗派の違うお寺に申し込むことは可能ですか?
A:はい。当サービスでは宗派・宗教に関わらずお寺を選択いただけます。
Q:生前に申し込むことはできますか?
A:はい。多くの方から生前にお申し込みいただいています。詳しくは「生前申込」のページをご覧ください。